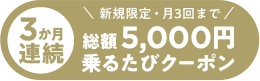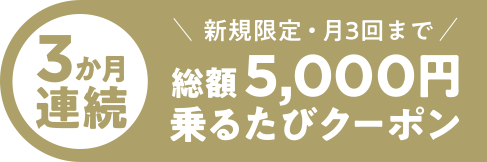タクシーに未来をのせて
TAXI GOes Next.
『GO』という名称には、行く、進む、
向かうといった言葉そのものの意味に加え、
タクシーに乗車されるお客様はもちろん、
運行を行う乗務員の方など、
サービスを使用する全ての人の笑顔や幸せなど、
未来をのせて走るという想いを込めました。
またロゴには、
人々の暮らしや未来を俯瞰で捉え集約した姿として、
地球をモチーフにデザインしました。
オンデマンド交通であるタクシーだからこそ実現できる、
百人百様の移動ニーズに寄り添ったサービスを
創造していきます。


JapanTaxiとMOVが
1つのアプリに!
『GO』は、『MOV』をベースとしたアプリで、
『MOV』提携タクシー車両に加えて
『JapanTaxi』アプリ提携タクシー車両へも
配車注文することができます。
一定期間は『GO』と並行して『JapanTaxi』アプリのサービス提供を行いますので、
『JapanTaxi』アプリユーザーの皆様は、サービスを継続してご利用いただけます。
なお、『JapanTaxi』アプリサービス終了時期が決まりましたら、
アプリユーザー様にご迷惑がかからないよう適切にお知らせいたします。


乗車位置を指定する
アプリを開くと、現在地の地図が表示されます。地図を拡大してピンを乗車位置に移動して次へ進みます。降車位置を指定することも可能です。
※AI予約は一部のエリアでのみご提供しています。

タクシーを呼ぶ
クーポンをご利用の場合※、この画面でクーポンを選びます。あとは[タクシーを呼ぶ]ボタンを押して、タクシーの配車依頼は完了です。
※配車依頼前にGO Payを設定、選択いただく必要があります。
タクシーの到着を待つ
到着予定時間が表示されるので、待ち時間を有意義に使えます。乗務員と直接メッセージのやりとりもできるので万が一の場合も安心です。

タクシーに乗る
タクシーが到着したら通知が届きます。あらかじめ降車位置を指定していれば乗車時に行き先を伝える必要もありません。

タクシーを降りる
GO Pay※を使えば、車内での支払いなしに到着後すぐに降車できます。
Google Play は Google LLC の商標です。
500円クーポンプレゼント中!
すでにMOVに登録済の方は対象外とさせていただきます。
※ クーポンのご利用には、GO Payの設定とあわせて、利用したいクーポンを選択いただく必要がございます。
※ 1回の乗車につきクーポンはお一つご利用いただけます。
※ クーポンには有効期限がありますので、登録後、期限をお確かめの上ご利用ください。